ウェビナーのやり方をゼロから解説|企画・準備・当日の進行まで完全ガイド
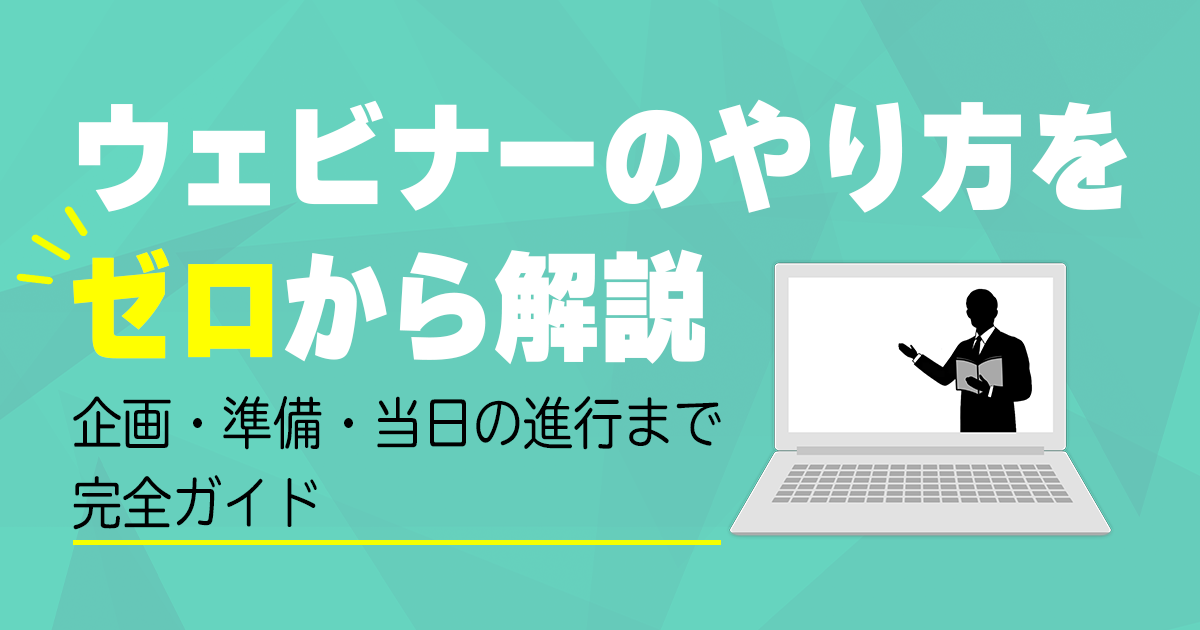
ウェビナーを開催したいものの、何から始めればよいのか分からない――そう悩む担当者は少なくありません。企画や構成の考え方、準備すべきもの、当日の進行や終了後の対応など、ウェビナーには押さえておくべき基本があります。
この記事では、ウェビナーのやり方をゼロから順を追って解説します。法人向けの初開催を想定し、企画の立て方、アジェンダの組み方、最適な時間帯、必要なツール、進行のポイントを整理しました。
目次
ウェビナーのやり方
ウェビナーとは?Web会議との違い
■ウェビナー(Webinar)とは
Webとセミナーを組み合わせた言葉で、インターネット上で開催する講演や説明会のことを指します。ZoomやMicrosoft Teamsなどの配信ツールを使って、企業が情報提供や商品説明、顧客教育を行う手段として使われています。
■Web会議との違い
情報の流れが一方向である点です。Web会議では、参加者全員が発言や画面共有を行うのが一般的ですが、ウェビナーでは主催者や登壇者がプレゼンテーションを行い、視聴者はチャットやQ&A機能を使って質問・コメントを送る形式が主流です。
Web会議は「社内の打ち合わせ」、ウェビナーは「講堂での講演会」のようなイメージです。
ウェビナー開催の基本ステップと所要時間
ウェビナーを初めて開催する際は、以下の流れに沿って準備を進めるのが基本です。
1.目的・テーマ・対象の設定
2.構成設計とアジェンダの作成
3.登壇者の選定と事前準備
4.必要なツール・機材・配信環境の整備
5.告知・集客・申込受付の準備
6.当日の進行と運営対応
7.終了後のフォローとリード活用
初回の場合は、告知開始から本番まで3〜4週間程度を見込んでおくと安心です。登壇者との調整や社内確認、集客用のバナー制作など、想定以上に時間を要する場面が多いため、余裕を持ったスケジュールをおすすめします。
ステップ①|目的・テーマ・対象の決め方
なぜウェビナーをやるのか?目的設定の考え方
ウェビナーを成功させるには、「なぜ実施するのか」という目的を明確にすることです。「誰に、何を、どう伝えたいのか」を整理し、社内で合意をとった上で企画を進めるのが基本です。ここが曖昧だと、テーマ選定や構成、集客施策にも一貫性が出ず、参加者に響かない内容になってしまいます。
目的は、次のようなパターンに整理できます。
・リード獲得(新規見込み客の開拓)
・商談創出(MQLからSQLへの転換)
・既存顧客の教育・活用促進
・パートナー・代理店向けの製品説明
・採用・ブランディングの強化
たとえば、リード獲得が主目的であれば、認知段階の顧客にとって魅力的な切り口や、課題を喚起するようなテーマ設計が必要です。一方、商談化が狙いなら、具体的なユースケース紹介や比較検討に効く内容が求められます。
ターゲットに響くテーマ・タイトルの作り方
ターゲットに関心を持ってもらうには、テーマとタイトルの設計にひと工夫が必要です。情報を届けたい相手(業種・職種・関心課題)を明確にしたうえで、「今その人が知りたいこと」「困っていること」に応える切り口を考えます。
テーマ設計のポイントは、以下の3点です。
・ペルソナの具体化
例:営業マネージャー/中堅SaaS企業/新規開拓に課題
・関心に寄せた課題設定
例:「広告依存を脱却したい」「商談率を上げたい」など
・行動を引き出すタイトル設計
例:「○○に困っていませんか?」「成功企業はこうしている」
タイトルには、「数字」「成果」「比較」「How-to」「他社事例」などの要素を盛り込むと効果的です。
例)
・失敗しない○○の選び方|導入前に押さえたい3つの視点
・【事例で学ぶ】○○の成果を最大化した企業の取り組み
・今日から使える!○○業務を効率化する5つの方法
参加者は「自分に関係がありそうかどうか」をタイトルだけで判断するため、キャッチーさよりも実利感と具体性を重視しましょう。
ステップ②|構成とアジェンダの設計

基本構成の型(導入→本編→Q&A→クロージング)
・導入(冒頭5〜10分)
目的の共有、登壇者紹介、視聴方法の説明など。
視聴者の緊張を解きつつ、得られる情報の価値を先に提示します。
・本編(20〜30分)
テーマに基づいたプレゼンテーションやデモ。
資料の流れに沿って展開しつつ、要所でチャット質問やクイズなどのインタラクションを加えると、 離脱防止にもつながります。
・Q&A(5〜10分)
事前質問やチャットからピックアップして回答します。
・クロージング(3〜5分)
まとめ、次アクションの提示(資料DL、個別相談、次回案内など)。
最後にアンケート回答の呼びかけも忘れずに。
話す順番や時間配分を設計しておくと、進行ミスや尺の乱れの予防になります。
視聴離脱を防ぐ時間配分と展開のコツ
参加者は、最初の10分で「このウェビナーは聞く価値があるか」を判断します。そのため、導入段階で何を得られるのか(ベネフィット)の明示が肝となります。
ちなみに、離脱が起きやすいのは以下のタイミングです。
・中盤で話が抽象的になる
・長時間、登壇者が話し続ける
・Q&A前に結論が見えてしまう
これらを避けるために、以下の工夫が有効です。
・スライド1枚につき1メッセージに絞る
・数分に1度、問いかけ・クイズ・チャット回答を挟む
・視覚的に飽きないよう図解・比較表を活用する
流れが単調にならないよう、「説明→図解→補足→問いかけ」のように文脈のリズムを設計しておくと、視聴の集中が続きやすくなります。
最適な開催時間と曜日・時間帯の選び方
ビジネス向けのウェビナーでは、平日の10〜11時台や14〜16時台に視聴率が高まる傾向があります。昼休みや終業間際は参加者の集中力が落ちやすいため、一般的には避けられることが多い時間帯です。
ただし、あえてランチタイム(12〜13時)に実施するケースもあります。多忙なビジネスパーソンにとっては、「食事をしながら情報収集できる」という意味で好評なこともあり、短時間・コンパクトな構成であれば有効な選択肢です。
曜日別では、火曜〜木曜が安定して集客しやすく、月曜は忙しい業務に埋もれがち、金曜は集中しづらい傾向があります。
参加者の業種・職種によっても最適な時間帯は変わるため、可能であれば過去データや営業チームからのフィードバックを踏まえて判断するとよいでしょう。
参加率・完走率を高める仕掛けとは?
登録したものの当日参加しないケースは、ウェビナーでよく見られる課題です。参加率(歩留まり)を高めるには、事前のリマインド設計と、当日の参加メリットを伝える工夫がカギとなります。
有効な施策
・前日・当日朝のリマインドメール(カレンダー登録リンク付き)
・冒頭で「最後に特典あり」と明示(例:資料DL、限定動画)
・Q&Aに参加した人への抽選プレゼント
・視聴後アンケートでのインセンティブ提供
「聞いて損はない」「最後まで見たい」と思ってもらえるよう、情報提供だけでなく“動機づけ”の設計を加えるのがポイントです。
ステップ③|登壇者の選定と話しやすい環境づくり
社内スピーカー・外部講師の使い分けと調整
ウェビナーの内容を誰が語るかによって、参加者の印象や納得感は大きく変わります。社内メンバーで登壇するのか、外部の講師を招くのかは、目的や訴求力、準備のしやすさなどを踏まえて判断する必要があります。
社内スピーカーを起用する場合
●メリット
・自社サービスへの理解が深く、質問にも柔軟に対応できる
・実際の顧客事例や現場視点を交えて話せるため、リアリティが出る
・外注費用がかからず、コストを抑えられる
●デメリット
・話し慣れていない場合、本番で緊張や言いよどみが出やすい
・プレゼン構成や話し方に不安がある場合、事前サポートが必要
・社内リソースを割かなければならない
外部講師を活用する場合
●メリット
・プレゼンに慣れており、進行がスムーズで安心感がある
・中立的・専門的な立場で話すことで、客観性や説得力が増す
・実績ある講師であれば、話題性や集客力が期待できる
●デメリット
・講演内容のトーンや方向性が自社とずれる可能性がある
・調整・すり合わせに時間がかかる
・講師料や契約調整など、コストと手間が発生する
登壇者への事前ケア|台本・練習・想定問答
話す内容が頭に入っていても、本番でスムーズに話せるとは限りません。スピーカーが安心して話せるよう、事前に以下の準備を行っておきます。
・簡易台本(トークスクリプト)作成
→ セリフではなく、「話すポイント」を箇条書きでまとめる
・1〜2回のリハーサル実施
→ 時間配分・言い回し・スライド操作を確認
・想定質問リストの共有
→ 質問に戸惑わないよう、事前に答えを用意しておく
初登壇の社員であれば、事前に社内メンバーを相手にした練習会を設けておくと、自信と安定感が格段に変わります。
プロが現場で実践する「話しやすい空間」の整え方
心理的な安心感をどうつくるかも意識しておきたいポイントです。
話しやすい環境づくりのコツ
・背景や映り込みに配慮する
オンライン配信では背景も視聴者の印象に影響します
仮想背景より、整えられた実空間が望ましいケースも
・照明とカメラ位置を調整する
顔に影が出ないよう自然光+リングライトなどを活用
カメラは目線の高さに合わせて配置
・周囲の音・通知を遮断する
マイクの音質だけでなく、話の妨げになる通知音・周囲の雑音を事前に排除
・運営からの声かけやアイコンタクト
配信中もチャットやサブ画面で「あと5分」「ゆっくり話してOK」などの合図を出すと、登壇者の安心材料に
慣れていない人ほど、環境の安心感がパフォーマンスに直結します。機材や音声の確認だけでなく、「安心して話せる」状態に整えることを優先しましょう。
ステップ④|必要な準備と配信体制の整え方

ツール・機材・環境|最低限そろえるべきもの
安定した配信には、ツールや機材を事前にそろえておくことが前提です。初開催では、「最小構成で確実に動かす」ことを優先しましょう。
最低限必要な構成
・配信プラットフォーム(Zoom、YouTube Live、Teams など)
用途や機能に応じて選定
・配信用PC(有線接続を推奨)
ブラウザ・配信ソフト・スライド操作が同時に安定動作するスペックが必要
・マイク
ノートPC内蔵マイクは音がこもるため、登壇者用には外付けを用意
・カメラ
画質よりも、目線の位置やライティングとのバランスが重要
・照明(リングライトなど)
顔の表情が明るく見えるよう、逆光や暗所を避けた照明配置を
・会議室
雑音や映り込みを防ぐため、静かで背景が整っている部屋を確保
エアコンや外音の干渉にも注意が必要
スライド・台本・進行表の作り方
配信当日に慌てないためにも、資料と進行に関するドキュメントは事前にそろえましょう。以下の3点が基本となります。
・スライド資料
1枚1テーマを原則とし、文字詰めよりも「見せたいこと」が一目で伝わるレイアウトを心がける
・登壇者用トークスクリプト(簡易台本)
原稿読みにならないよう、「話すポイントだけ」を短文で整理(印刷して手元に置くと安心)
・進行表(タイムテーブル)
「開始◯分〜:〇〇氏登壇」「〇分〜:Q&A」といった形式で、全体の流れと時間配分を明示(運営メンバー間の共有も必須)
運営メンバーの役割分担と連携体制
初開催では、些細な行き違いが思わぬトラブルにつながることがあります。たとえば「誰がチャットを見るのか」「何分で話を切り替えるのか」といった細かい段取りを詰めておくだけで、当日の安心感がまるで違ってきます。
| 役割 | 担当業務 |
| 配信担当 | 配信開始・画面切り替え・音声チェックなど |
| 司会・進行 | 冒頭説明、Q&A誘導、クロージング対応 |
| チャット対応 | 質問・コメントの拾い上げ、回答補助 |
| タイムキーパー | 進行時間のモニタリング、遅延の調整 |
| トラブル対応 | 機材トラブル・通信不良時の対応サポート |
オンライン会議ツールのチャット機能や、Googleスプレッドシートなどでリアルタイムに進行共有できる仕組みを用意しておくと安心です。
トラブル防止のためのチェックリスト
トラブルを防ぐには、前日・当日のチェックリストを事前に用意しておくのが効果的です。以下は、最低限確認しておく項目の一例です。
・配信機材(PC・マイク・カメラ・照明)の動作確認
・配信ツールのバージョン更新・ログイン確認
・登壇者の通信環境チェック(Wi-Fiではなく有線が理想)
・スライド・台本・進行表の最終確認と共有
・Zoomなど配信ツールの権限設定(ホスト、共催者など)
・録画設定の事前確認
・バックアップ要員・予備機材の準備(可能であれば)
トラブルは完全には避けられませんが、「起きたときにすぐ対応できる準備」があるだけで、進行への影響を最小限に抑えることができます。
ステップ⑤|配信ツールの準備・設定
オンライン配信の現場では、Zoomがもっとも一般的に利用されています。しかし、配信の目的や視聴者層、求められる機能に応じて、YouTube Live、Microsoft Teams、Webex、Vimeoなど、さまざまなプラットフォームが活用されています。
それぞれのツールには特有の機能や制限があるため、用途に応じて最適なプラットフォームを選び、配信環境を適切に設定することが重要です。
Zoomウェビナーの基本設定と招待URLの作成
Zoomには「ミーティング」と「ウェビナー」の2つのモードがあり、登壇者と参加者の役割が明確に分けられる「ウェビナー」機能が適しています。
基本的な設定フロー
1.Zoomアカウントで「ウェビナー」ライセンスを契約(有料)
2.新規ウェビナーを作成(タイトル、日時、概要などを設定)
3.登録フォームのカスタマイズ(参加者情報の取得項目を設定)
4.登壇者(パネリスト)を事前に登録
5.参加者用の招待URLを発行・共有
ウェビナー開催中は、パネリストのみが音声と映像を使用でき、参加者は視聴・チャット・Q&Aに限定されるため、進行の混乱を防ぎやすいというメリットがあります。
また、登録制にしておくと、事前の参加者管理やフォローがしやすくなるため、マーケティング目的であれば「登録必須」の設定を推奨します。
▶Zoomウェビナーの詳しい設定手順については、こちらの記事をご覧ください。
【永久保存版】Zoomウェビナーとは?使い方と設定方法
リハーサルと練習セッションの重要性
当日に安定した進行を実現するためには、事前リハーサルが必須です。とくに、以下の3つの観点から練習しておくことがポイントです。
配信環境の動作確認
1.マイク・カメラ・スライド・共有画面・録画設定・インターネット回線など、全体の接続状況をテスト
2.スピーカー・進行のタイミング合わせ
誰がどこで話し始め、何分話すのか
Q&Aの受け渡しやクロージングの段取りも確認
3.緊急対応時の動き方を共有
音声が出ない、資料が表示されないなど、トラブル時の対処方法をチーム内で事前に決めておく
リハーサルは、本番と同じ時間帯・機材で行うことで、光の入り方や通信状況まで含めた実践的な確認ができます。
他ツール(YouTube Live、Teams等)利用時の注意点
Zoom以外の配信ツールを使う場合も、それぞれの特徴と制約を把握しておく必要があります。
| ツール名 | 特徴・メリット | 注意点 |
| YouTube Live | 無料で大規模配信が可能。アーカイブが自動で残る。SEO効果や拡散力も高く、視聴にアカウント登録不要で参加ハードルが低い。 | 視聴者情報の取得ができず、双方向性に欠ける。チャット管理も制限あり。 |
| Microsoft Teams | 社内会議や教育用途に適し、Officeとの統合が強み。操作に慣れている人が多い。 | 外部参加者にとっては導線が複雑。アカウント作成が必要なケースも。 |
| Vimeo / Webex等 | 高機能を重視する場合に有効。独自ドメインやパスワード保護など、ブランディング性・セキュリティに強み | 多くが有料プラン前提。英語UIや設定項目が複雑な場合あり。 |
選定時のポイントは、「目的との相性」と「社内メンバーの扱いやすさ」です。
たとえば、参加者の情報をしっかり取りたい場合は、YouTubeよりZoom。デザイン性やブランドイメージを重視するならVimeo。社内向けでTeams慣れしている組織ならTeamsでも十分成立します。
ステップ⑥|当日の進行とトラブル対応
本番前の最終確認|リハーサル・接続・役割確認
本番開始の1〜2時間前から余裕をもって準備を始めるのが基本です。以下のような項目を最終確認しておきましょう。
・配信ツールの起動・接続チェック
ZoomやTeamsなどを立ち上げ、マイク・カメラ・スライド共有の動作を確認
・登壇者・運営メンバー全員の接続確認
リハーサル同様、音声や画面のトラブルがないかを当日もチェック
・各人の役割・進行の最終すり合わせ
司会の入り方、チャット対応のタイミング、終了後のクロージングまで細かく確認
・録画設定のON確認(必要に応じて)
録画の保存先や容量制限、録画の権限なども事前に調整しておくと安心
進行表(タイムテーブル)を手元に置いておくと、予定通りに進めやすくなります。
スムーズな進行を支える段取りと実況的判断
完璧に準備をしても、想定通りに進まないこともあります。登壇者の話が延びたり、予想外の質問が出たりしたときは、現場での判断力が問われます。
進行を円滑に進めるための工夫
・時間が押した場合にどこを短縮するかを決めておく
Q&Aの件数を絞る、クロージングを簡潔にまとめるなど、あらかじめ判断基準を共有しておく
・司会が“全体の舵取り役”を担う
話の区切りをつけたり、登壇者に「そろそろまとめに入ってください」と伝えたりする役割を担う
・チャット・Q&Aへのリアクションで場の温度感を拾う
コメント数や質問の傾向から、参加者がどこに関心を持っているかを察知し、流れに応じた対応を行う
・事前に質問を用意しておく
参加者からの質問をあらかじめ募っておいたり、想定される質問を事務局側で用意しておくことで、当日質問が出なかった場合でも、間を持たせながらスムーズに進行できます。また、登壇者もあらかじめ質問内容を把握しておけるため、焦らず落ち着いて回答できるというメリットもあります。
緊張している登壇者をうまくサポートし、見えていない参加者の反応を汲み取って場を整えるのが、進行役の大切な役割です。
よくあるトラブルとその実践的な対処法
ウェビナーでは、以下のようなトラブルがよく発生します。
| トラブル | よくある原因 | 対処法 |
| 音声が出ない | マイク未接続・ミュート設定・音声設定ミス | 再接続、PC側・ツール側両方の設定を確認 |
| スライドが表示されない | 画面共有の設定ミス | 一度画面共有を終了し、正しいスライド画面を選び直して共有する。複数画面がある場合は選択ミスに注意。 |
| 登壇者が接続できない | 回線不良・遅延 | 代理の読み上げ担当を用意、時間調整で対応 |
| 録画されていない | 手動設定忘れ | 予備として運営側でも録画を走らせておく |
| 動画の音声が流れない | 共有時に「音声を含める」にチェックし忘れ | 動画共有時は「音声を共有」の設定をONにする。別PCから再生する場合は、ミキサー経由で音声出力を切り替える必要あり。事前に接続・ルーティング確認を。 |
| チャットが機能しない | 権限設定ミス・ツール側の不具合 | 権限設定を確認し、必要に応じて再読み込みまたは別ツールで代替対応 |
| 参加者から「音が聞こえない」という問い合わせがくる | 参加者側の音声設定(ボリューム・ミュート・出力先など)が正しくできていない | 待機画面中にBGMを流しておくことで、視聴環境のチェックを促す。「音声が聞こえない場合の対処法」を、開始前スライドやチャット欄に掲示しておくと親切。 |
重要なのは、参加者にはなるべく気づかせずに処理することです。万一トラブルが発生した場合も、司会や運営が落ち着いて対応することで、不信感や離脱を最小限に抑えられます。
進行中に参加者を飽きさせない工夫
ウェビナーでは、参加者がカメラOFF・マイクOFFで視聴するため、「聞き流し状態」や「離脱」になりやすい傾向があります。以下のような仕掛けを組み込むことで、視聴の集中度を保ちやすくなります。
・途中で問いかけやチャット投稿を促す
例:「この中で当てはまる方、チャットで“1”と打ってください」
・ミニクイズやアンケート機能を活用
Zoomの投票機能や、外部のライブ投票ツールを活用して参加意識を高める
・参加者を一時的にパネリストに昇格させる
特定の質問や体験共有などのタイミングで、希望者をパネリストに昇格し、カメラと音声をONにして発言してもらう。視聴者側に緊張感と参加意識が生まれる。
・話し手の切り替えを意識する
20分以上の単独トークは飽きやすく、司会や別の話者が差し込むとリズムが生まれる
・スライドの構成に変化をつける
図解・グラフ・チェックリストなどを適度に入れ、画面に動きを持たせる
一方的に話すだけのウェビナーでは、記憶にも印象にも記憶にも残りません。参加者の反応を引き出す仕掛けがあると、内容への理解も深まり、満足度も自然と上がっていきます。
ステップ⑦|終了後のフォローと活用

アンケートと参加者リストの回収・整理
ウェビナー後のフォローは、成果を“資産化”するための重要フェーズです。特に、アンケートと参加者データの活用次第で、リード育成や商談化率が大きく変わります。
・参加者リストの整理
Zoomなどの配信ツールからダウンロード可能な、登録者・参加者・視聴時間などのデータを集計する
・アンケートの実施と集計
終了直後にURLをチャット送信 or システムで自動表示
┗内容の満足度
┗理解度・関心の高かったパート
┗今後聞きたいテーマ
┗資料・個別相談の希望有無
・コメント・質問のテキスト化
Q&Aやチャットで得られた参加者の声を記録し、次回企画や営業活動の参考にする
アンケートは視聴直後がもっとも回答率が高いため、終了5分前から案内を始めておくのが効果的です。
録画・アーカイブの公開判断と注意点
録画データは、アーカイブとして活用することで、開催後もリード獲得や育成に利用できます。「ライブ参加できなかったが内容には関心がある」層に向けて、録画コンテンツを活用することで接点を継続できるのがアーカイブ活用の強みです。
ただし、公開にあたっては以下の点に注意が必要です。
・登壇者・講師の事前許諾
発言内容や顔が映っている場合、録画・再利用の可否を契約または口頭で確認しておく
・アーカイブ用の編集(無音・ノイズカットなど)
録画データをそのまま公開するのではなく、冒頭の無音部分や裏方のやりとりなどをカットして整える
・視聴ページの設計(フォーム経由にするかどうか)
リード獲得が目的なら、フォーム登録後に視聴できるよう設計する
・公開期間・コンテンツの鮮度確認
市場動向や製品情報が古くなった場合、非公開に切り替える運用も検討する
リード獲得や商談化につなげる導線設計
ウェビナーは、単なるイベントではなくマーケティング施策の一部です。終了後の動線が設計されていなければ、せっかくの参加者データも活かしきれません。
代表的な導線設計
・アンケート回答者に個別フォローのメール
希望者には営業担当が早期にコンタクト。資料送付や日程調整を進める
・スコアリングによる優先度づけ
視聴時間・アンケート内容・資料DL有無などから、商談化可能性を判定
・ナーチャリングメールの設計
すぐには商談に至らない見込み客に対し、アーカイブ・関連資料・次回セミナー案内などを段階的に送付
・SalesforceやMAツールへのデータ連携
CRMやMAツールと連携することで、リードの一元管理・分析が可能になる
ウェビナー後の動き方は、事前に営業チームとすり合わせておかないと、せっかくの参加者情報も活かしきれません。実際、「フォローできる体制が整わないなら、今回は見送る」といった判断が、結果的に正解になることもあります。
よくある失敗と成功の分かれ道
初開催で失敗しがちなパターンと回避策
初めて開催する際、準備不足や認識のズレが原因で失敗するケースが多く見られます。ありがちな失敗パターンと、その回避策をまとめました。
| 失敗パターン | よくある原因 | 回避のための対策 |
| 集客が伸びない | ターゲット不明確/告知タイミングが遅い | 開催1か月前から集客計画を立て、ターゲットに刺さる訴求設計を行う |
| 途中離脱が多い | 時間配分や構成にメリハリがない | 15分ごとに変化を入れ、視聴者の関心を引きつける設計にする |
| 音声や映像の乱れ・配信トラブル | 機材テストやチェックリストの欠如、不安定なネット環境 | 前日・当日の通信状況を含めた技術チェックと、トラブル時のバックアップ体制を整えておく |
| 進行がスムーズにいかない | 運営スタッフが配信ツールや機材操作に不慣れ/司会進行がぎこちない(素人対応) | 使用ツールの事前練習と、操作手順のマニュアル化/プロ司会者の起用や、進行用スクリプトの用意・練習 |
| スピーカーが話しづらそう | 台本・リハーサルが不足している | スクリプト共有と1~2回の事前練習を徹底する |
| フォローが弱く成果につながらない | 終了後の動線が設計されていない | アンケート・録画活用・営業連携を事前に準備しておく |
配信自体はうまくいったのに、リードも商談も動かない。その多くは、終了後の活用まで見据えた設計が不足しているのが原因です。「配信の先」をどこまで描けていたかが、ウェビナーの成否を分けます。
成功するウェビナーに共通する3つの視点
成果を出している企業のウェビナーには、いくつかの共通点があります。
1.視聴者目線で企画されている
社内の都合ではなく、「このテーマなら視る価値がある」と思わせる構成になっている
顧客課題ベースで、自己紹介や自社説明に時間を使いすぎない傾向が高い
2.当日の進行がプロフェッショナル
司会とスピーカーの役割が明確で、スムーズな進行に加え、視聴者とのインタラクションもうまく設計されている
話しすぎず、聞きすぎず、テンポを保ちながら進める工夫が随所に見られる
3.終了後の活用が徹底されている
録画・スライド・質問内容をアーカイブし、メールマーケティングや営業資料として2次活用し、1回の開催を「資産」として繰り返し活かしている
ウェビナー成功の鍵は「準備」と「その後」
ウェビナーは、話す内容や段取りを整えるだけでなく、参加者との接点をどう生かすかまでを含めて設計するものです。
本番をスムーズに運ぶための準備と、終了後のリード活用やフォロー体制。この両方がそろって初めて、ビジネス成果につながる施策になります。
| 参加率も満足度も高める、ウェビナー運営を代行します。企画設計から当日の運営、終了後の活用まで、 ウェビナー運営のパートナーとして丁寧にサポートします。 私たちは、現場に根ざしたノウハウで、主催者も参加者も納得できるウェビナーの成功を支えます。 ➡︎フロンティアチャンネルのウェビナー、ライブ配信代行サービスについて詳しくはこちら |
監修者プロフィール
野本 彩乃(のもと あやの)
株式会社フロンティアチャンネル 代表取締役
音楽クリエイター、アナウンサー、イベントディレクターを経て、2015年に制作会社「株式会社フロンティアチャンネル」を創業。
ライブ配信事業では、官公庁・公共団体・大手企業のウェビナーや配信を数多く支援。
音楽・音声・映像制作から配信運用、独自のITツール開発まで、幅広いクリエイティブを手がける。
「世に残るコンテンツを創る」を信念に、現場視点とクリエイティブを融合させた運営支援を行っている。





